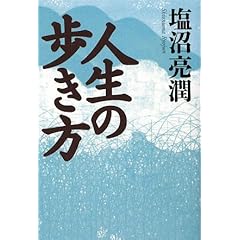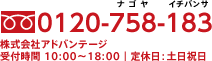大阿闍梨・塩沼亮潤さんの講演会に行ってきました。
マリオットホテルのボールルームが満席でしたので、500名以上参加されたのではないかと思います。
講演を聴いて驚いたのは、塩沼亮潤さんが千日回峰行に挑まれた理由の一つに、人間関係の悩みがあったということ。
どうしても苦手な人がいて、うまく接することができない。
そうした、多くの人に共通するようなよくある悩みについて、千日回峰行を満行することで何かわかるのではないかという思いがあったそうです。
あまりに普通で驚きました(笑)
そして、お寺に務める僧侶であっても、普通の人と同じような人間関係の悩みがあるということにも。
千日回峰行は、一旦始めると、怪我であれ病気であれ、1日でも辞めることは死を意味します。
常に自害用の短刀をもって行に当たると言うことなのですが、塩沼さんは、何回か死にそうな目にあっても、辞めたいとか、手を抜きたいと思ったことはないそうです。
行をすること自体が好きであったとも話されていました。
千日回峰行を終えた翌年、塩沼さんは、四無行という難行にも挑まれます。
四無行というのは、9日間の断食・断水・不眠・不臥を続けながら、お経を唱え続けるという苦行です。
この四無行も見事に満行された後、やっと、塩沼さんは、苦手意識があった人と和解することができたそうです。
そのとき、塩沼さんは、苦手に想っていた相手の心の中にある真心・愛の部分にのみ語りかけるということを行った結果、長年のわだかまりが解けていったと言うことでした。
お釈迦様は、この世にあるあらゆる難行苦行を経験した後、「難行苦行は無駄である」と悟りを拓かれました。
それでもなお、千日回峰行のような難行苦行に挑む人がいる。
人間は、やはり、自ら体験することでしか、理解できない生物なのかもしれません。
ただ、最終的には実生活レベルにおいて、自らが体験したことを活かして、よりよい意識レベルで行きていくことが最も重要なのだと思いました。
塩沼さんは、月間致知の対談で、次のように仰っています。
『人生も行も、つまることろ、すべて人を恨まない、人を憎まない、人のせいにしない覚悟を持つことが出発点だと思っています』
何かを人のせいにした瞬間、自分の成長は停まります。
それは、逃避であり怠惰です。
千日回峰行のような難行苦行の場合、逃避や怠惰=死を意味します。
行というのは、逃避や怠惰を身体や意識の中から消し去ることを目的としているのかもしれませんね。
素晴らしいお話を、ありがとうございました。